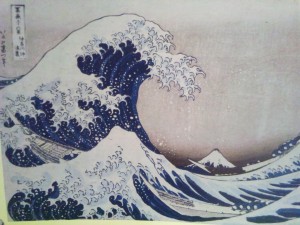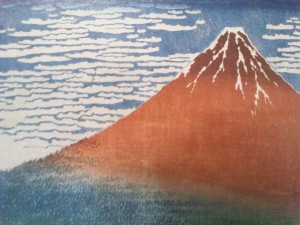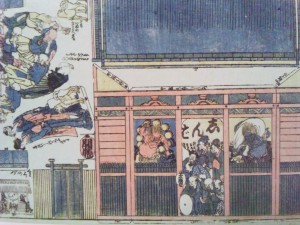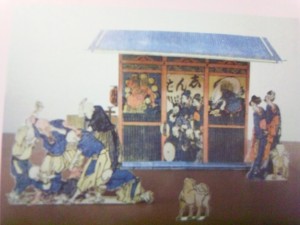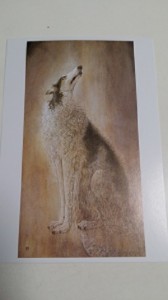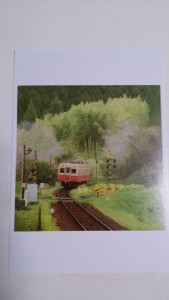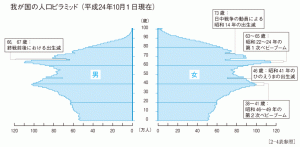こんばんは
昨日
毎年恒例のキャンプに行ってきました。
今回は ユーテックさんから 3人参加していただき 計14人で
Let’s Go!! \(^o^)/
『1日目』
場所は 奈良県 『下北山スポーツ公園キャンプ場』
現地に行くまでに 途中で スーパーで買いだしに
お酒や野菜など購入。 みんなでワイワイ 買い物も新鮮で 楽しかったです。
それから 今回泊る コテージへ
中に 入ってみると 思っていたより 広くて サイコー!
なんと! 一階の奥で バーベキューなんかも出来ちゃいます。
二階に上がると メチャクチャ広くてビックリ!ヽ(^o^)丿
テンション上がりまくりです。 (写真じゃ伝えきれませんが・・・)
しばらくして バーベキュー開始!
毎回 調理担当で みんなに おいしいものを 提供してくれている
栗ちゃん! サイコー!\(^o^)/
こちらも みんなで ワイワイとおしゃべり ・・・
そして それぞれ みんな 夢の中へ・・・ 1日目 終了 。
(実は 数名 夜中に熱いトークが繰り広げられていました。
内容は ナ・イ・ショ!)
熱い・熱すぎるよ~
『2日目』
今日は 朝から 栗ちゃんの 特製バーグだ!
あとは ハッシュドポテトに卵焼き!
これらをパンに挟んで 特製栗バーガー 出来上がり!
うまいぜー 栗ちゃん!
今回もおいしい料理を ありがとー。<(_ _)>
朝食後
みんなで 後かたずけ 。(みなさん ご苦労様です。)
その後 一服して コテージを後に・・・
上北山温泉があるしたの川へ すごく天気がよく気持ちよかったです。
(午前中だったので 川の水が冷たく 寒かったです。)
(テレッ) みんなでワイワイ遊んだ後は
みんなで 温泉へ入り ほっこり。
そして 解散へ・・・
今回は 天気にも恵まれ 人にも恵まれ 楽しかったです。
今回の交流を通して 普段見れない面や考えなんかも 徐々に
すり合わさっていくような 感じがしました。
良いキャンプでした。
また 明日から 暑い日が 続くそうですので みなさん
水分を取って 乗り越えましょう!
それでは
N.yamaguchi