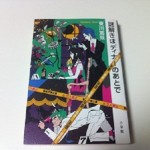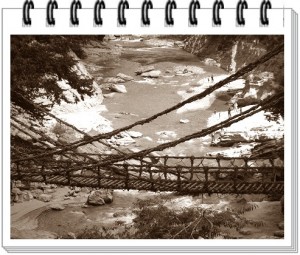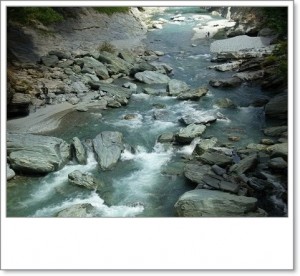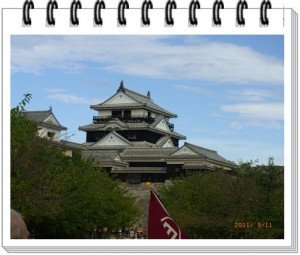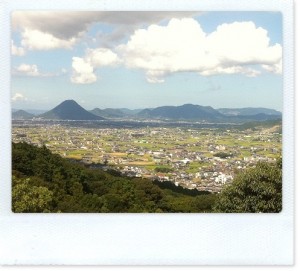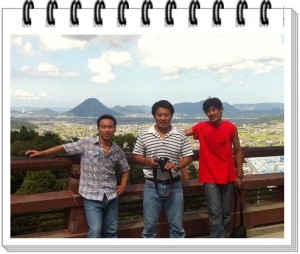むかし、むかし・・・ある人達がそれぞれ馬を3頭持ち寄って、1頭ずつ競争させることになりました。
そこで、ある側近が主人に向かってこう助言しました。
「相手の1番強い馬に対しては、自分の1番弱い馬をぶつけましょう。そして、相手の2番目に強い馬に対しては、自分の1番強い馬をぶつけましょう。最後に相手の1番弱い馬に自分の2番目に強い馬をぶつけましょう。」
結果は、2勝1敗で勝ち越すことができました。
この逸話は、「孫子の兵法」にふれた事がある人達には有名な話です。
相手を知り、己を知って、最適な戦術を施す話としてわかりやすい例ですね。
今、TPP参加の問題が世間を賑わせています。
その中で農業が受ける影響に対して、専門家の話になんとなく違和感を感じました。
専門家いわく「北米のように大規模農場で栽培する農産物の価格に対して、日本の狭い農地で育てた農産物は価格で対抗できない。だから、日本の農業は壊滅的な影響を受ける。」のだそうです。
この話をまともに受ける場合、一つの条件があると思います。
それは、「出来上がった農産物が同等品質、もしくは、ほとんど差がない」と言うことです。
では、北米の大規模農場で栽培される農産物と日本の小規模農場で育てられた農産物は全く同じレベルなのでしょうか?
その答えは、生産農家の方が一番わかっていると思います。
味については、それほど差がない可能性もありますが品質は味だけで測れません。
目の届く範囲できめ細かく手入れされて育てられた有機栽培の農産物などは、むしろ大規模農家が苦手とする分野です。
有機栽培の農産物は、食材に対して敏感な北米のセレブに対して好評を得る可能性も十分にあると思います。
「流通力をもつナレッジ・カンパニー(知識を基盤とする会社)にならなければならない。製造の力では、製品を差別化しきれない。」
これは、ドラッカーの有名な言葉の一つです。
TPP参加にあたって、農業盛衰のポイントは生産農家にあるのではなく、むしろ流通にあるのではないでしょうか?
日本の農作物が持つ潜在的な付加価値をいかに価格に反映できる流通を築くか?によって、今後の農業の行方は変わってくると思います。
要は、コスト額ではなくコスト率の問題です。
先日、パナソニックがテレビ事業の縮小を発表しました。
日本の電機メーカーのテレビパネル事業は、台頭する中国や韓国の企業との間に熾烈な価格競争を強いられてきました。
おそらく品質に関しては、優位に立っていたと思います。
ところが熾烈なシェア争いの中で、相手が優位な価格競争に引きずり込まれた感があります。
結局、相手の得意な部分と自分達の苦手な部分とで勝負せざるを得なくなり、このような結果になってしまいました。
価格競争に陥らないためのブランド戦略は、日本人が苦手とする部分かも知れません。
しかし、「自分達の強みを相手の弱みにいかにぶつけていくか?」と考えた時に、日本人が得意な分野をブランド化していくことは重要なことだと思います。
日本の農業も価格の勝負ではなくて品質の勝負に持って行くことができれば、十分勝機はあると思うのですが・・・。
「製造の力では、製品を差別化しきれない・・・」
ドラッカーのつぶやきが心に響きます。
K.yamatani